突然始まった介護生活「えっ、何から始めればいいの?」

母が転倒して入院してから、急に介護のことを考え始めました
そんな50代の私が直面したのは、「介護保険って、何から始めればいいの?」という戸惑いでした。
実は多くの人が、同じように”必要になるその時”まで制度をよく知らないまま迎えているんですよね。
この記事では、私の実体験を交えながら、介護保険の仕組みと申請の流れを「同じ立場のあなた」に向けて、等身大でお話しします。
**「介護保険どう使う?初心者の私が体験した申請の流れと注意点」**について、リアルな声をお届けしますね!
この記事で分かること
- 介護保険って誰が使えるの?(意外と知らない条件)
- 実際の申請手続きってどんな感じ?
- 使えるサービスと「あれ?これ有料なの?」な話
「特定疾病」って何?40代・50代の私たちも対象なの?
母の件があってから調べて分かったのですが、40〜64歳の私たちも介護保険が使えるケースがあるんです。
ただし条件があって、「特定疾病」という厚生労働省が定めた16種類の病気が対象。
「え、私たちも?」と思いましたが、実際にはこんな病気が当てはまります。
よく聞く病名だと:
- 初老期の認知症(若年性認知症)
- 脳卒中などの脳血管疾患
- パーキンソン病
- 関節リウマチや骨折を伴う骨粗しょう症
- がん末期、筋萎縮性側索硬化症など
判断は医師の意見書や訪問調査で総合的に決まります。
でも大切なのは病名だけじゃなくて、「毎日の暮らしでどんなことに困っているか」なんです。
病気が軽くても、本人や家族が「これは大変だな」と感じているなら、まずは相談してみる価値ありです。
私も最初は「まだ大丈夫かも」と思っていましたが、思い切って申請して本当によかったと思っています。
申請は誰ができる?「私が代わりにやってもいいの?」
介護保険の申請は、本人じゃなくても大丈夫!家族が代わりに手続きすることができます。
実際、私のように家族が動くケースの方が多いかもしれませんね。
申請できる人はこんな感じ:
- 本人(もちろんOK)
- 家族(配偶者や子ども)
- 親族や近所の方(委任状が必要)
- 介護施設の職員さん
- 地域包括支援センターの方と一緒に
私の場合、母は「よく分からない」と不安がっていたので、私が代わりに市役所の介護保険課に行きました。
必要だったのは「申請書」「母の保険証」「かかりつけ医の情報」など。
認知症が進んでいる方でも、家族がサポートすれば全然問題ありません。
地域包括支援センターの方も親身になって相談に乗ってくれるので、一人で抱え込まずに頼ってみてくださいね。
大切なのは「困ってから」じゃなくて「困る前」に動くこと。
早めに準備することで、家族みんなが安心できる介護生活につながります。

家族で一緒に動いたから、安心して進められたわ
申請の流れ – 私の体験談で解説します
介護保険の申請って、一つずつ手順を踏めば意外と難しくありません。
私が実際に体験した流れを、「こんな感じだったよ」というリアルな目線でお話ししますね。
申請前に家族でやったこと
まず、私たち家族がしたのは「現状把握」でした。
家族会議で確認したこと:
- 母の最近の困りごとを兄弟で共有
- かかりつけ医の病院・診療科の確認
- 通院歴の整理
- 市役所の窓口の場所調べ
- 介護保険証の在り処確認
兄と私で「最近、母がつまずきやすくなった」「外出を嫌がるようになった」という話をして、まずは主治医の先生に相談しました。
先生から「軽い認知症の傾向がありますね」と言われた時は、やっぱりという気持ちと、でも具体的に動けるという安心感がありました。
その後、市役所に電話して「介護保険の申請をしたいのですが」と聞いたら、丁寧に教えてもらえました。
家族で話し合ったからこそ、母も安心して手続きに臨めたと思います。
実際に集めた書類と期間
書類集めは思ったより簡単でした。1週間あれば十分そろいます。
私が提出した書類:
- 介護保険認定申請書(市役所でもらえます)
- 母の介護保険被保険者証
- 本人確認書類(保険証とマイナンバーカード)
- かかりつけ医の情報(病院名・医師名)
- 家族申請なので委任状
市役所で申請書をもらって、家で記入。分からないところは窓口で「これってどう書けばいいですか?」と聞いたら、職員さんが親切に教えてくれました。
保険証や身分証は家にあるものでOK、通院している病院の情報も診察券を見れば分かります。
書類提出後、約1週間で訪問調査の連絡が来ました。
「そんなに早く?」とちょっと驚きましたが、流れに乗っていけば大丈夫です。
窓口で実際に聞かれたこと
「どんなことを聞かれるんだろう」と不安でしたが、日常生活の話が中心で構えすぎる必要はありませんでした。
聞かれた内容:
- どんなことで困っているか
- 1日の過ごし方
- 誰と一緒に住んでいるか
- 通院している病院について
- 介護で心配なことは何か
私は「最近、母がつまずきやすくて転倒が心配で」と答えたら、職員さんが「それは大変ですね。どんな時につまずくことが多いですか?」と詳しく聞いてくれました。
母が答えにくそうな時は、私が「家ではこんな感じで」と代わりに説明しても全然問題なし。
職員さんは「できること」と「難しいこと」を整理して考えてくれるので、安心してお話しできました。
準備は特に必要ありません。普段の生活の中で感じていることを、そのまま伝えるだけで大丈夫です。
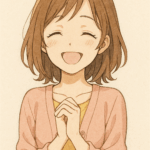
不安だったけど、優しく聞いてくれてホッとしたわ
サービスを使ってみて分かったこと
介護保険の申請が通って、実際にサービスを使い始めると「申請して良かった!」と心から思いました。
でも同時に「え、これも自己負担なの?」という驚きもありました。
リアルな体験談をお話ししますね。
実際に使ったサービスと感想
私たちが利用したサービス:
- デイサービス(週2回)
- 訪問介護(掃除・買い物サポート)
- 福祉用具レンタル(歩行器)
- 住宅改修(玄関に手すり設置)
- ショートステイ(月1回)
デイサービスは母にとって「お出かけ」の感覚。「今日はデイサービスの日ね」と楽しみにするようになりました。
同年代の方との会話で笑顔が増えて、家でも明るくなったのが一番の変化です。
玄関の手すりは本当に設置して良かった!「段差が怖かったけど、これがあると安心」と母も喜んでいます。
訪問介護のヘルパーさんには、掃除や買い物をお願いしています。私の負担も減って、母との時間をゆっくり過ごせるようになりました。
「介護=大変」だと思っていたけど、サービスを使うと「みんなで支える」という感じに変わります。
「え、これも有料なの?」想定外の出費
介護保険があっても、すべてが無料ではありません。ちょっと驚いた出費もありました。
気をつけたい自己負担:
- サービス利用料の1〜3割負担
- デイサービスの昼食代(1回500円程度)
- 対象外サービスは全額自己負担
- 住宅改修の一部自己負担
- 福祉用具購入の条件付き補助
デイサービスの昼食代が毎回かかるのは知らなくて「あれ?」と思いました。
訪問介護も、普段の掃除や料理はOKだけど、大掃除や庭の手入れは対象外。「どこまでが介護保険の範囲なの?」と最初は戸惑いました。
でも、ケアマネジャーさんに「これは対象ですか?」と遠慮なく聞けば、丁寧に教えてもらえます。
お金のことは後でトラブルにならないよう、事前にしっかり確認することが大切ですね。
制度を上手に使うコツ
介護保険は「使って終わり」じゃなくて、「どう使うか」が重要だと実感しています。
私が心がけていること:
- ケアマネさんとの連絡はマメに
- サービス内容の定期見直し
- 母の気持ちを一番に考える
- 疑問や不満は早めに相談
- 合わないと感じたら変更も検討
最初のデイサービスが母に合わなくて、施設を変えたことがあります。「わがまま言っちゃダメかな」と思ったけど、ケアマネさんに相談したら「合う・合わないはありますよ」と別の施設を紹介してくれました。
今では「今日はお友達に会える日」と楽しみにしています。
制度に私たちが合わせるんじゃなくて、私たちに合わせて制度を使う。
そう考えると、介護がぐっとラクになりますよ。

制度を知るだけじゃなく、使い方も工夫したいわね
最後に – 同じ立場のあなたへ
50代で突然始まった介護生活。最初は「どうしよう」の連続でした。
でも介護保険という制度があることで、一人で抱え込まずに済んだし、母も私も前向きに過ごせています。
大切なのは「完璧を目指さない」こと。
制度を上手に使いながら、自分たちらしい介護のスタイルを見つけていけばいいんです。
もし今、同じような状況で悩んでいる方がいたら、まずは地域包括支援センターや市役所に相談してみてください。
一人で悩まず、みんなで支え合える介護を目指しましょう。
あなたの介護生活が、少しでもラクで笑顔の多いものになりますように。


コメント